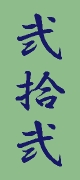
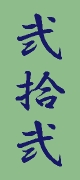
数日後――
梅月は鬼哭村を訪れた。
あの後、弥勒は一晩休むと、九角に報告をするのだと言う桔梗と一緒に村に戻ってしまっていた。
かなりの深手を負っていたのだ、梅月は勿論、桔梗も随分止めたのだが、弥勒は決して首を縦には振らず、止める方が根負けした次第である。
「おや?」
村に戻ったのだから、てっきり工房にいるものと思って訪れた梅月は、見事に肩透かしを食う羽目になった。
工房は、しばらく人が寝起きした気配が感じられない。
弥勒の気配は元々希薄だが、さすがにここで生活しているとは思われなかった。
戸締まりはしていなかったが、盗人などいない村では出かける時も戸締りしないことがほとんどだ。
仕方なく、誰か弥勒の行方を知っている者がいないかと、梅月が館を訪れるとすぐにある一室に案内された。
「君が人の世話になるなんて、珍しいこともあったものだね」
「当たり前だよ。自分で寝起きも出来ない怪我人が、あんな引っ込んだところに一人でこもっていられちゃ、その方が迷惑じゃないか」
梅月が弥勒の枕元で思わず素直な感想を述べると、案内してきた桔梗がぴしりと言った。
布団の中の弥勒は縁側の方を向いたままで、桔梗と目を合わせようとしない。
「…君にも怖いものがあったと言う訳だね」
梅月は、喉の奥で笑った。
弥勒は黙りこくったままだ。
黙り込んでいるのはいつものことだが、この沈黙はいつもの沈黙とは質が違う。
「それじゃ先生、無理しないように見張ってて下さいな」
と、言い残して桔梗が立ち去ると、途端に弥勒が首を元に戻す。
よほど口やかましく怒られて懲りたのだろう。
見た目よりはるかに年経た女が本気で怒ったら、逆らえる者は少ない。
さすがの弥勒も例外ではなかったということだ。
その様を想像して、梅月がもう一度小さく笑うと、弥勒が視線だけで睨んだ。
その視線に、梅月は咳払いして話を逸らす。
「怪我の具合はどうだい?」
「そろそろ動かさなければ、弱って困る」
言いながら、弥勒は包帯に包まれた腕を上げて見せた。
最初に見た時よりは巻いた包帯の厚みが随分薄くなっている。
順調に回復しているとは思われるが、外せないということはまだ完治には程遠いのだろう。
「でも、無理は禁物だよ」
梅月は気つかわしげな表情で尋ねる。
「放った陰気によって内側から裂けた傷だ。そうそう直るまい」
弥勒の腕は、内側から皮膚が捲れるような傷ばかりだった。
自ら放出する気によって、彼の腕は内側から裂けてしまったのだ。
本来の媒介である面があればそんなことにはならなかったのだろうが、術具もなしに大きすぎる力を行使できるほど、弥勒は術師として研鑽していない。
その上に、御門の枷をかけられていた。
運が悪ければ気が暴走し、弥勒自身ごとこの世から吹き飛んでも不思議はなかった。
この程度、と言うにはあまりに深手だが、この程度で済んでよかったと、梅月達は胸を撫で下ろしたものだ。
「秋月――御門とは話をつけたよ」
弥勒は聞いているのかいないのか、身じろぎ一つしない。
「当主にはなる。だが、秋月の家に戻る訳ではない。秋月が僕の力を必要として、僕自身が僕でなければことが済まぬと判断した時だけ、僕が出向き、それ以外の時は、今の通りの気侭をすると言うことで話がついた」
と、弥勒が首を巡らせて、梅月の上にひたと視線を据えた。
「随分君に都合がいいように出来ているな」
「気づいたかい」
「秋月が望んでも、君が認めなければ出向かずに済むとは、よくあの男が許した」
「元々それが僕の出した条件だったんだよ。一時御門の出した条件を呑まざるを得なかったが、御門自身が御破算にしてくれたからね」
梅月は薄く笑った。
「もう一つ、どうしても君に言っておきたいことがある」
弥勒が梅月へ視線を向けた。
「君は自分に名前がないと言った。だが、それが本来名づけられたものではなくとも、長く名乗ればそれは己の名になる」
視線で先を促され、梅月は意を決して口を開く。
「『弥勒万斎』は既に君の名だよ」
すると弥勒は鼻を鳴らして言った。
「別に名が欲しいと思ったこともないが」
「初めて聞いた時は、正直菩薩の名を名乗るとは随分身の程知らずだと思ったものだが、今は、『弥勒万斎』と言う名は君に相応しいと、僕は思うよ」
「俺が俺であることに、名は何の意味もなさん」
弥勒はついと縁側の方へ顔を背けた。
「ただ、面があればそれで充分」
その態度があまりにもらしくて、梅月は微苦笑する。
「今日はそれを言いに来たんだ」
この後、弥勒がどうしようと構わない。
構いたいが、構わせてはくれないだろう。
「無論、他に望む名があるのなら、それを名乗ればいい。君は何でも好きな名を名乗れる。選ぶ自由が君にはある」
しかし言霊使いとして、どうしてもそれだけは告げておかねばならなかった。
「さて、そろそろお暇するよ。館殿に御挨拶もせず、こちらに来てしまったからね」
梅月が鮮やかに裾を払って立ち上がる。
「まあ、気ままをすると言ったところで、秋月の名を背負う以上はさすがにそう気軽に出歩くことは出来なくなるだろうからね。これからは君の邪魔をすることも減ると思うよ」
そう言って踵を返した梅月の背中に、抑揚のない声が投げかけられる。
「そろそろ新作にとりかかる」
梅月の言葉など耳にも入れていないような言葉だった。
さすがに心中穏やかならず肩越しに振り向くと、弥勒が起き上がろうとしていた。
慌ててその背を支えに戻ると、微かに触れた弥勒の腕がぴくりと動いた。
やはり痛みが完全に消えた訳ではないらしい。
「傷に響くのではないかい?」
「それでもいつまでも寝込んでいては、面が打てなくなる」
途端、梅月の瞳が翳る。
一人で寝起きすらままならない事態になっても、弥勒の執着は面にだけに向いていることを思い知らされるからだ。
どれほどに覚悟を決めようと、心の痛みは消えはしない。
だが。
「仕事の邪魔をしない限りは、君の好きだけ、飽きるまで来るがいいさ」
構ってはやらんがな、と、弥勒はぼそぼそと呟く。
「どんな名を名乗ろうと、どんな面を被ろうと、俺は俺で、君は君だ」
その言葉に。
梅月は破顔一笑して弥勒を抱き締める。
弥勒は、抱き返してはくれなかったけれども、振り払おうとも、しなかった。